
この記事では、女性に多い「冬うつ」について詳しく紹介しています。温かい季節はそれなりに活動的なのに、冬になると毎年不調を感じていませんか?
「寝過ぎてしまう」「甘い物が無性に食べたくなる」「動くのが億劫で、やる気も出ない」。
冬うつの症状改善や対処法など、参考にして下さいね。
目次
冬うつの特徴は?
冬うつの正式名称は「季節性感情障害(SAD)」で、特に女性に多い症状です。元来の「うつ病」との違いや症状の特徴について紹介します。
秋から冬にかけて鬱っぽくなる
温かい春や夏はそうでもないのに、秋から冬の寒い季節になると鬱っぽくなるのが特徴です。寒い季節に限定して、「疲れやすい」「やる気が出ない」「気分が落ち込みやすい」という症状が現れます。
春先になると少しずつおさまり、また冬が近づくと再発する…というふうに、繰り返し症状が起こるケースも多く、「反復性冬季うつ病」と呼ばれたりもします。
食欲の亢進
「うつ病」の場合は食欲が落ちるという症状がありますが、冬うつは逆です。食欲が増進し、炭水化物や甘い物などをドカ食いしてしまいがち。
ただでさえクリスマスや忘年会、お正月などといったご馳走を食べる機会が多いこの時期に、冬太りを加速させてしまいます。
女性にとっては、ただただ厄介な症状ですね。
とにかく眠い
うつ病では「不眠」も特徴的ですが、冬うつの場合は逆。眠くてたまらず、睡眠時間が長くなります。10時間以上の睡眠をとっても、まだ眠気が取れないということもよくある話です。
また、うつ病の症状である早朝覚醒(夜明け頃など、朝早すぎる時間に目が覚める)とも逆で、朝起きることが非常につらく感じたりもします。
参考サイト:季節性感情障害(SAD)
冬うつの症状だ現れる原因
冬になるとやる気が起きず、動くのもつらい。甘い物がやたらと欲しくなって、眠くてたまらない。そうなってしまう原因は、一体どこにあるのでしょうか?
日照時間の短さ
冬うつは、日照時間の短くなることによって、脳内のセロトニンが不足することが原因の1つです。太陽が出ている時間が短くなることによって、当然ながら人が光に当たる時間も減少します。その影響で、神経伝達物質であるセロトニンが不足し、うつのような症状が現れるというわけです。
実際、冬が長くて暗くなる北欧では、冬うつの発症率が高いことが知られています。
参考サイト:「冬うつ」を1分で吹き飛ばす、4つのご自愛術
【セロトニンとは】
セロトニンは、精神のバランスに大きく関わる神経伝達物質です。不足するとうつ病になりやすいのはもちろん、心が不安定になったり、暴力的になったりもします。
活性化させるには食物から摂取する(後述)か、日光に当たるか、軽い運動をするなどの方法があります。
また、うつ病の治療としては向精神薬のSSRIの服用が奨励されており、セロトニンの分泌を促す働きがあります。
冬うつで太るのは、代謝が落ちて脂肪を溜めやすくなるから
セロトニンが不足することで体のあらゆる機能が低下して代謝が下がり、脂肪を貯めやすくなります。
便秘の原因にもつながるため、なかなか厄介です。
ただでさえ秋や冬は、体温を保つために脂肪を蓄えやすい時期でもあるのに、とんだ追い打ちというわけですね。
参考サイト:身体機能をボロボロにするセロトニン不足!
甘い物や炭水化物が脳内セロトニン濃度を高める
甘い物や炭水化物が欲しくなってしまうのも、やはりセロトニンの不足が引き金になって起こることという説があります。
糖分を摂るとセロトニンが一時的に増加するため、短時間ではあるものの快楽を覚えるようになります。
しかし、あくまで一時的な快楽に過ぎない為、「足りない」「もっともっと」と体が余計に渇望するようになります。脳内のセロトニン濃度を高めて、落ち込みやうつ状態から気分を上げようとする本能なのかも知れません。
眠くてたまらないのは、メラトニンのせい
気温の低い冬は、起床時に体を温めるのに時間がかかります。体温が上昇しないと、覚醒状態になるまでが遅くなり、「なかなか起きられない」「朝がつらい」という状態になってしまいます。
また、冬は暗くなると分泌が盛んになる「メラトニン」も原因です。メラトニンは眠気を引き起こすため、日照時間が少なくなって暗い時間が長くなる日が続くことで、眠くてたまらない冬うつの症状につながるというわけです。
参考サイト:もしかして冬季うつ病?冬によく食べる・寝る・太る人は要注意
つらい冬うつの症状の対処法
毎年のように冬うつを繰り返している女性は、「今年もそろそろかな?」と、感覚で分かるかも知れません。不眠や過食、気分の落ち込みなどのつらい症状を和らげるための対処法を知っておきましょう。
日光を浴びる
日照時間が短い冬こそ、太陽の光を積極的に浴びましょう。特に朝起きた時、朝日を浴びると体内時計のスイッチが入って、活動モードに入りやすくなります。
また、明るい光を浴びることでセロトニンが活性化し、冬うつの改善につながるということでもあります。
病院では高照度光療法器具での治療を取り入れているところもあります。
参考サイト:日本を元気にする光療法の総合サイト
アーシングをする
「健康や自律神経に良い」と、近年話題になっているアメリカ発祥の健康法が、アーシングです。やりかたは非常にシンプル。裸足で芝生や土などの大地に立ったり、軽く歩いたりするだけです。
私たちの体には、微弱電流が流れています。それらがパソコンや携帯電話などの電化製品から発せられる電磁波によって、日々悪影響を受けていると言われています。
それによって、本来は流れていないといけない微弱電流が体内に溜まってしまい、体の不調などを起こしやすくしてしまうのです。
アーシングとは、溜まった体内電流の有害酵素を放出し、脚の裏から「地球(Earthアース)」のエネルギーを受け取ること。
地球は草花や生き物の命を育む、自由電子を放出しています。靴を脱ぎ、裸足になって足の裏から自由電子を受け取ると、体内電気のバランスも整います。
風邪や生理痛はもちろん、うつ病にも効果府があるという報告もあるため、ぜひ活用してみましょう。
冬場は寒いですが、太陽が出ている日中に行うととても気持ちがいいです。
参考サイト:アーシング – 地面とつながる健康法
食べ物でセロトニンを摂取する
脳内で作られるセロトニンを増やすには、必須アミノ酸であるトリプトファンが必要です。体内で合成されないため、食べ物から意識して摂取するようにしましょう。
トリプトファンが多く含まれる食品は、牛乳やヨーグルトなどの乳製品、納豆や豆腐などの大豆製品、バナナやさつまいもなどです。
また、白米にもトリプトファンは豊富に含まれています。パン食派の人も、この機に玄米や雑穀を混ぜた白米を食べるようにしてはいかがでしょうか?
あまりにもつらいならメンタルクリニックを受診する
セルフケアに限界を感じたり、仕事や日常生活であまりにも支障をきたすようであれば、思い切ってメンタルクリニックを受診しても良いかも知れません。
診断によっては抗うつ薬や漢方薬が処方され、症状そのものを緩和することができるでしょう。
また、信頼できる主治医に症状を話すことで、気持ちが楽になることもあります。1人で抱え込むのがつらいなら、専門家の力を借りましょう。
頑張れない時は頑張らない
究極はこれです。「頑張れない時は頑張らない」。仕事など、給料が発生する場ではある程度体に鞭打って頑張らなければならないかも知れません。
でも、部屋の掃除や家事などは、「今日はここまで」とある程度手を抜いたり、加減をしたりしても良いのではないでしょうか?
冬うつでつらい上に、年末年始などはただでさえ慌ただしい時期。くれぐれも、疲れをため込み過ぎないように気を付けましょう。
まとめ
冬になると気分が落ち込み、眠気や食欲の増進が起こるのであれば、冬うつの傾向があるかも知れません。女性に多いとされているので、思い当たるなら意識して対処する必要があります。
積極的に日光を浴びてセロトニンを増やしたり、場合によってはクリニックを受診したり。でも究極は、「頑張れない時は頑張り過ぎない」ということ。
無理をせず、つらい冬を乗り切って下さいね。
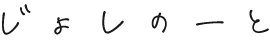








コメント